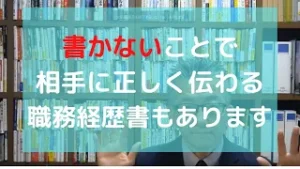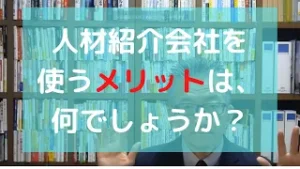ものの見方はTKC──自分をマネジメントするための思考の軸
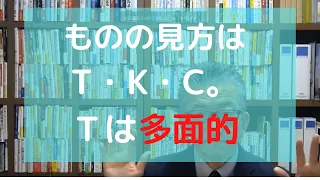
ものの見方はTKC──自分をマネジメントするための思考の軸
私たちは日々、無数の判断を下しながら生きています。仕事においても、家庭においても、人間関係においても、判断の積み重ねが未来を形づくっていきます。だからこそ、「ものの見方」を誤ると、思いもよらない方向に進んでしまうことがある。これは、私自身が日々痛感していることです。
そのリスクを避けるために、私は「TKC」という三つの視点を大切にしています。これは、自分自身をマネジメントするための思考の軸であり、判断の精度を高めるためのフィルターでもあります。
「T」──多面的に見る力
まず最初の「T」は、「多面的に見る力」です。
世の中のあらゆる事象は、一つの面だけでは語り尽くせません。人材評価にしても、ある人が「優秀だ」と感じる一方で、別の人は「扱いづらい」と感じるかもしれない。企業に対する印象も、業界内の立場や個人の価値観によって、まったく異なるものになることがあります。
このような違いは、単なる主観の違いではなく、情報の偏りや先入観によって生じることが多いのです。つまり、私たちは知らず知らずのうちに「一面的な見方」に囚われてしまっている。
だからこそ、私は意識的に「多面的に見る」ことを心がけています。ある人やある事象について判断を下す前に、できる限り多くの角度から情報を集め、異なる立場の人の意見を聞き、背景や文脈を理解するよう努めています。
具体事例:採用面接での気づき
あるとき、採用面接で「物静かで反応が薄い」候補者に出会いました。第一印象では「積極性が足りない」と感じましたが、念のため、過去の職場での評価や、同僚の声を確認してみると、「冷静で着実」「周囲の信頼が厚い」との声が多くありました。実際に入社後は、安定した成果を出し続け、チームの潤滑油のような存在になりました。
この経験は、「多面的に見る」ことの重要性を教えてくれました。一つの面だけで判断していたら、貴重な人材を見逃していたかもしれません。
「K」──根本的に考える力
次に「K」は、「根本的に考える力」です。
何かの目的に向かって進んでいるとき、予期せぬ問題や障害が必ずと言っていいほど現れます。その都度、私たちは対処しながら前に進もうとしますが、時にその「対処」が目的化してしまうことがあります。
例えば、ある業務の効率化を目指していたはずが、いつの間にか「ツールの導入」そのものが目的になってしまう。あるいは、顧客対応の改善を目指していたのに、「クレーム処理の迅速化」だけに注力してしまう。
こうしたズレは、根本的な目的を見失っていることから生じます。だからこそ、「それって、根本的にはどうなの?」と自問することが重要なのです。
具体事例:サービス改善の迷走
以前、あるサービスの利用者満足度が下がったとき、「FAQの充実」「チャットボットの導入」など、表面的な対策ばかりを講じていました。しかし、根本的な原因は「サービスの提供内容が利用者の生活状況に合っていない」ことでした。つまり、機能ではなく“文脈”がズレていたのです。
そこで、利用者の声を丁寧に拾い直し、「誰が、どんな状況で、何に困っているのか」を再定義。結果として、サービス設計そのものを見直すことになり、満足度は大きく改善しました。
根本に立ち返ることで、対処療法ではなく“本質的な解決”ができたのです。
「C」──長期的に判断する力
最後の「C」は、「長期的に判断する力」です。
私たちはどうしても、「今の成果」や「すぐに得られる果実」に目が向きがちです。今日の売上、今月の数字、今回のプロジェクトの成果──これらはもちろん重要ですし、短期的な成果を求めること自体が間違いではありません。
しかし、短期的な成果だけを追い求めると、長期的に見て誤った判断をしてしまうことがあります。例えば、コスト削減のために人材育成を後回しにした結果、数年後に組織力が低下してしまう。あるいは、目先の売上を優先して無理な営業を続けた結果、顧客との信頼関係が損なわれてしまう。
こうした事態を防ぐために、私は「長期的に考える」ことを意識しています。判断を下す際には、「この選択は5年後、10年後にどう影響するだろうか?」という視点を持つようにしています。
具体事例:価格改定の判断
あるとき、サービス価格を値下げすることで一時的な集客を狙う案が出ました。確かに短期的には成果が出る可能性がありましたが、長期的には「価格=価値」というブランドイメージが崩れるリスクがありました。
そこで、値下げではなく「価値の再定義と発信」に注力する方針に切り替えました。結果として、価格は維持しながらも、より深くサービスの魅力を伝えることで、継続的な利用者が増え、ブランド力も向上しました。
短期的な誘惑に流されず、長期的な視点で判断したことが功を奏した例です。
TKCを活用した判断ミスとその修正エピソード
もちろん、私自身も過去にTKCを意識できず、判断を誤ったことがあります。
あるとき、あるスタッフの業務態度に不満を感じ、「この人は向いていない」と早々に評価を下してしまいました。これは「T=多面的に見る」ことを怠った結果でした。後に、別の部署のリーダーから「彼は裏方での調整力が抜群」と聞き、実際に配置転換してみると、見違えるほど活躍し始めたのです。
また、あるプロジェクトで、途中のトラブル対応に追われるあまり、「K=根本的な目的」を見失い、いつの間にか“トラブル処理”が目的になってしまったこともあります。進捗はしているのに、成果が出ない。そこで一度立ち止まり、「そもそも何のためのプロジェクトだったか?」を再確認。すると、目的に対して手段がズレていたことに気づき、軌道修正することで、最終的には成果に繋がりました。
さらに、「C=長期的な視点」を持たずに、短期的な売上を優先して広告を打った結果、一時的な集客はできたものの、サービスの本質を理解していない利用者が増え、継続率が下がってしまったこともありました。以後は、広告の打ち方も「誰に、どんな価値を、どう伝えるか」を長期的な視点で設計するようになりました。
TKCは「自分を守るための思考法」
「T=多面的に」「K=根本的に」「C=長期的に」
この三つの視点は、私にとって「自分を守るための思考法」です。判断を誤れば、信頼を失い、方向性を見失い、時間や資源を浪費してしまう。だからこそ、日々の判断においてTKCを意識することで、冷静さと確かさを保つようにしています。
もちろん、完璧にできるわけではありません。時には一面的に見てしまうこともあるし、根本を見失うこともあるし、短期的な成果に心を奪われることもあります。
でも、そんなときこそ「TKCに立ち返る」。それが、自分自身をマネジメントするための習慣であり、信念でもあります。
そして、このTKCの視点は、自分自身だけでなく、組織やサービス設計、クライアント支援にも応用できます。たとえば、サービスを設計するときに「多面的にユーザーの状況を捉え」「根本的なニーズを見極め」「長期的な関係性を築く」ことを意識すれば、より本質的で持続可能な価値提供が可能になります。
ものの見方を間違えないために。
そして、自分自身を見失わないために。
TKCという思考の軸を、これからも大切にしていきたいと思います。
ではまた。
◇キャリアカウンセリングから書類添削、面接対策まで
無料で転職のアドバイスを受けてみませんか?
無料転職登録ページからご連絡いただければと思います。