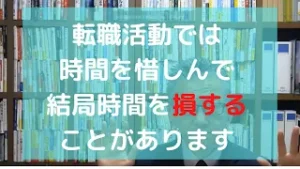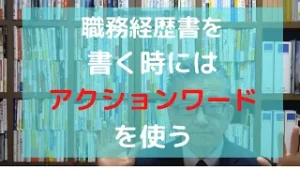職務経歴書を「逆から書いてみる」と、自分自身を正しくわかっていただけるかもしれない——順番が変わると、伝わり方も変わる
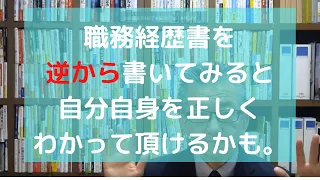
職務経歴書は、転職活動において最も重要な書類のひとつです。履歴書が「形式的なプロフィール」だとすれば、職務経歴書は「あなたの仕事人生を語るストーリー」です。どんな経験を積み、どんな成果を出し、どんな価値を提供できるのか——それを伝えるための媒体です。
一般的には、職務経歴書は時系列で「過去から現在へ」と書くのが基本とされています。最初の職歴から順に並べていくことで、キャリアの積み重ねや成長の軌跡を示すことができます。
しかし、職務経歴書には履歴書のような厳密なフォーマットの決まりはありません。目的はただひとつ——「この人に逢ってみたい」と思ってもらうことです。
その目的に照らして考えたとき、「逆から書いてみる」つまり「現在から過去へと遡る形で書く」ことで、より効果的に自分を伝えられるケースがあるのです。
職務経歴書の本来の目的とは?
まず、職務経歴書の本質的な目的を改めて確認しておきましょう。
それは、「自分の経験やスキルを通じて、企業にとって価値ある人材であることを伝えること」、そして「この人に会って話を聞いてみたい」と思わせることです。
つまり、単なる事実の羅列ではなく、「読み手の興味を引き、納得させる構成」が求められます。どんな順番で書くか、どこに重点を置くかは、すべて「伝えるための戦略」なのです。
逆時系列で書くメリット:3つの視点
では、職務経歴書を「逆から書く」ことで得られるメリットとは何でしょうか。主に以下の3つが挙げられます。
1. 直近の職歴が最もアピールできるケースが多い
転職活動において、企業が最も重視するのは「今のあなたが何をできるか」です。過去の経験ももちろん重要ですが、直近の職歴こそが「現在のスキルセット」や「即戦力性」を示す材料になります。
逆時系列で書くことで、最初に目に入るのが「最新の職務内容」になります。これにより、企業側は「この人は今こういうことができるのか」とすぐに理解でき、興味を持ちやすくなります。
2. 第一印象で「いいんじゃない」と思わせる構成ができる
採用担当者は、限られた時間の中で大量の書類をチェックしています。だからこそ、最初の数行で「この人は面白そうだ」「話を聞いてみたい」と思わせることが重要です。
逆時系列で書くことで、最初に「最も魅力的な職歴」や「直近の成果」が目に入るため、第一印象を強くすることができます。これは、書類選考突破の可能性を高める大きな要素です。
3. 絶対に読んでほしい情報を先に提示できる
時系列で過去から書いた場合、最初の職歴があまり魅力的でない場合、読み手が「この人は難しいかも」と判断してしまい、最後まで読まれないことがあります。
逆時系列であれば、「今の自分の強み」や「最近の成果」を最初に提示できるため、読み手が興味を持った状態で過去の職歴に進んでくれます。つまり、「読んでほしい情報を確実に読んでもらえる」構成が可能になるのです。
実際の構成例:逆時系列と時系列の比較
ここで、同じ職歴を持つ人が「時系列」と「逆時系列」で職務経歴書を作成した場合の違いを見てみましょう。
時系列(過去→現在)
1. 2010年〜2014年:株式会社A(営業職)
新規開拓中心。個人顧客向けの提案営業。月間目標達成率80%。
2. 2014年〜2018年:株式会社B(営業職)
法人営業に従事。中小企業向けのソリューション提案。年間売上1億円達成。
3. 2018年〜現在:株式会社C(営業マネージャー)
チームマネジメント、戦略立案、部下育成。部門売上前年比120%達成。
→ 読み手は、最初に「個人営業の経験」から入り、徐々にスキルアップしていることはわかるが、直近の成果にたどり着くまでに時間がかかる。
逆時系列(現在→過去)
1. 2018年〜現在:株式会社C(営業マネージャー)
チームマネジメント、戦略立案、部下育成。部門売上前年比120%達成。
2. 2014年〜2018年:株式会社B(営業職)
法人営業に従事。中小企業向けのソリューション提案。年間売上1億円達成。
3. 2010年〜2014年:株式会社A(営業職)
新規開拓中心。個人顧客向けの提案営業。月間目標達成率80%。
→ 読み手は、最初に「マネージャーとしての成果」に触れ、「この人は即戦力になりそうだ」と感じる。過去の職歴は補足情報として自然に読まれる。
このように、順番を変えるだけで「伝わり方」が大きく変わるのです。
逆時系列が向いている人・向いていない人
もちろん、すべての人に逆時系列が向いているわけではありません。以下のようなケースでは、逆時系列が効果的です。
向いているケース
- 直近の職歴が最もアピールポイントになる
- キャリアアップしてきた流れが明確である
- 過去の職歴にあまり自信がない
- 即戦力としての印象を強くしたい
向いていないケース
- 過去の職歴にこそ強みがある(例:大手企業での経験)
- キャリアチェンジをしていて、過去の職歴から説明したほうが自然
- 一貫性のあるストーリーを重視したい場合
つまり、「どちらが正しいか」ではなく、「どちらが自分を正しく伝えられるか」が判断基準になります。
職務経歴書は“戦略的に構成する”もの
職務経歴書は、単なる履歴の羅列ではありません。読み手に「この人に会ってみたい」と思わせるための“戦略的なプレゼン資料”です。
だからこそ、順番や構成にこだわることは、単なる形式の問題ではなく、「伝える力」の問題なのです。
逆時系列で書くことで、あなたの“今”を強く印象づけることができる。それが、書類選考突破の第一歩になるかもしれません。
最後に——「順番を変える勇気」が、伝わり方を変える
「この人に会ってみたい」と思ってもらえる職務経歴書とは、読み手の視点に立って構成されたものです。時系列で書くのが当たり前だと思っていた方も、一度「逆から書いてみる」ことで、自分の強みがより鮮明に伝わるかもしれません。
順番を変えることは、単なるテクニックではありません。それは「自分をどう見せたいか」「どこに価値があるのか」を見つめ直す作業でもあります。逆時系列で書くことで、今の自分の価値を最初に提示できる。それは、読み手の判断をポジティブに導く力になります。
まとめ:職務経歴書は「構成」で勝負が決まる
- 職務経歴書は履歴書と違い、自由度が高い
- 目的は「逢ってみたい」と思ってもらうこと
- 逆時系列で書くことで、直近の職歴を強く印象づけられる
- 第一印象を良くすることで、選考突破の可能性が高まる
- 絶対に読んでほしい情報を先に提示できる
- 経歴内容によっては時系列の方が効果的な場合もある
- 順番は「自分をどう伝えるか」という戦略で決めるべき
職務経歴書は、あなたのキャリアを伝えるだけでなく、あなたの“考え方”や“伝える力”そのものを映す鏡です。だからこそ、構成にこだわることは、単なる形式の話ではなく、あなた自身の価値をどう届けるかという本質的な問いでもあります。
「逆から書いてみる」。その一歩が、あなたの魅力をより正確に、より強く、相手に届けるきっかけになるかもしれません。
ぜひ、職務経歴書の構成を見直す時間を取ってみてください。あなたの“今”を、もっとも効果的に伝える順番は、どこから始めるべきか——その問いが、次のチャンスへの扉を開くかもしれません。
ではまた。
◇キャリアカウンセリングから書類添削、面接対策まで
無料で転職のアドバイスを受けてみませんか?
無料転職登録ページからご連絡いただければと思います。